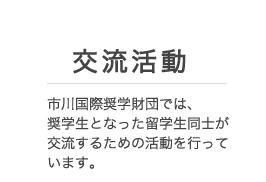3月交流会

3月5日(土)14時から3月の交流会をオンラインにて行いました。
まず、みんなで近況報告を行い頑張っていることを共有した後、
今月のゲスト岸田ひろ実さんに加わって頂きました。
岸田さんには、ご自分の経験をお話し頂き、さまざまなテーマについても
意見交換を行いました。
楽しくも厳しい留学生活のなかで、いろんな想いを抱えている奨学生のみなさん。
岸田さんから大きなちからを頂いたようです。私もそのうちの一人です。
では、みなさんのエッセーをご覧ください
3月交流会エッセー
-
劉 泓子
先日のオンライン交流会で、岸田さんの貴重なお話を聞かせていただきました。これまであまり考えたことのない分野のお話であり、たくさんの刺激と有益な気付きを与えていただきました。
交流会の前に、ネットで岸田さんの経歴を調べたら、壮絶すぎてひたすら驚いておりました。まだ何の面識もない人のことではあるが、神様のあまりの残酷さに少し心を痛めました。そしてご本人が行なっている活動から察するに、おそらくご自分の過去の辛い出来事を話して、いかに苦難から乗り越えたか、という趣旨の講演をされていると予想しました。私自身も含めて、おそらく多くの人は過去のちょっとした辛いことでもあまり思い出したくないし、人に話すことで返ってフラッシュバックして気分が沈むこともあるかと思います。想像を絶するほどの辛い経験を人前で話せるようになり、さらに聞く人に勇気と前向きな気付きを与えられるようになるまでは、きっと辛い中大変な努力をされてきたでしょう、とまず尊敬の念を抱きました。
実際当日にお話を伺ってみると、まずは彼女の明るい笑顔に心を打たれました。きっと長い年月をかけて、人知れない莫大な努力をして、辛い涙と絶望の闇から道を開いてここに来られたと感じました。その素晴らしい精神力ももちろんですが、最も感心したのは、彼女がご自分の経験から社会にある差別や、他人への思いやりなどの問題について話された部分でした。その中で一番印象に残った言葉は、ダウン症の息子さんのことを「障害ではなく、ただ勉強が不得意な子」と話しました。非常にハッとさせていただいた言葉でした。得意、不得意、さらに一般的にいうと、人間みんなそれぞれ違うだけだということに、気付きました。勉強は不得意でも、心優しい子であることは変わりない。障害を持つ方に配慮を配ることはもちろんですが、一方世間は、障害ということに敏感に反応しすぎたかもしれません。
道路整備など、日常生活の面において、障害者の身体面のサポートはある程度できていても、心の面ではまだまだ意識の足りない部分かもしれません。私自身も彼女の話を聞くまでは、障害を持つ方への接し方を考えることはなかった。これからは、障害を持つ方はもちろん、他人に対して、お互いの得意不得意をあまり気にせず、異なる部分を尊重しながら、思いやりの心で接するように心がけたいです。
-
崔 睿岩
2022年3月5日、貴財団の交流会を参加させていただき、オンラインで岸田ひろ実さんと交流ができて、非常に光栄でした。岸田さんは自分の経歴を紹介していただき、高齢者や障害者への向き合い方の指導や講演などで活躍していることから、深い感動を受けます。今回の交流会で、印象深いことは二点があります。
一つは、絶望から抜け出すことです。自分の今までの人生で、困難、挫折、失敗は当然頻繁にあります。特に、今は博士後期課程ですので、研究に関する問題とか、論文を書けないこととか、徹夜しても必要な資料を探せないこととか、「もう無理だ」、「もう限界だ」の状況は常にあります。たまに、なぜ後期課程に進学するのか、諦めたら人生が順調に進めるかもしれないという考えも出ます。さらに、研究室の同期や先輩に比べると、自分の研究プロセスは遅いので、やはり自分では無理だと思いました。このような状況は私から見ると、もうすでに絶望でしょうと考えました。しかし、交流会で岸田さんの経歴を聞いたら、自分の経歴は絶望ではないです。ただの小さい挫折です。これらの挫折を乗り越えれば、前へ進めるかなと思います。従って、これからは、積極的な態度で人生を思考し、他人と比べなく、自分のペースで人生を過ごそうと考えています。
二つは、ユニバーサルマナーに関する説明です。これは非常に共感しています。やはり、相手にとっては、自分が勝手に提供するものより、相手の要求によって手伝う方がかなり尊重的ですよね。しかし、社会では、このようなマナーができる人はまだ多くないと思います。困難に遭って、ただ友達とかと話したいとき、相手がいつも「大丈夫よ。もうちょっと頑張ったら絶対いける」のような話をくれると思います。ただ、頑張ることは自分の欲しいものではありません。頑張ったらいけることは誰でも知っていますが、困難に遭った時の自分にとっては慰める言葉ではないです。相手が勝手にくれました。ユニバーサルマナーに関する説明を聞いてから考えたのは、自分にとって、周りは「頑張ったらいける」と言ってくれても、頑張りたくない時は頑張らなくていいので、たまには休んでください。今まで十分頑張ったからです。さらに、自分は必ずマナーを守って、相手を尊重し、手伝う前は相手の要求を聞くのが大事です。
今回の交流会によって、岸田さんとも、みなさんとも交流ができ、かなり勉強になりました。今後も、前向き、積極的に生活を過ごそうと思います。
-
JIN Chihao
この機会を通して、岸田さんの講座を聞きながら、色々な思いを出します。岸田さんがたくさんの人生の困難と絶望の気持ちを克服して、私は本当にインスピレーションしました。
私たちの人生にはたくさんの困難とチャレンジがあって、それに向かっての態度と決心が一番重要なものだと思います。例えば、重大な絶望に遭って、その後どうやって生活を続くのか、どうやって解決するのかいいなどの問題が私たちが考えなければならないことです。現在の生活ペースが速すぎて、そんなことを思う時間が大体ないと思います。一旦非常に難しいことに直面した時に、ペースは突然に遅くなって、多くの思いが浮かび上がります。この場合には、人々の気持ちとムードは不安定になる可能性が高いです。このような状況で、私たちの態度と選択がとても重要です。態度と言えば、積極的に家族や友人に伝えること、助けを求めること、自分の考えをよくシェアーすることです。そうすると、私は私ではなく、家族と友人の支えとサポートも一緒に傍にあります。選択は自分の考え方とやり方です。困難を克服すると絶望の痛みを抑えるために、私たちは多くのことをすることができます。例えば、自然に近づくことで、気分転換として、心とムードが安定になるかもしれません。気を散らすための新しいスキルや知識を学ぶことで、自分が新たな可能性を発見することができて、体がだんだんリフレッシュになります。
二年前の2020年には、新型コロナウイルスが全世界で広がりました。誰もが多くの影響をうけていて、人生も多少に困難な状況に陥っていました。ストレスと不安とともに、私もその時に悪かった気持ち時々持っていた。今振り返ると、その経験が一番暗かったです。あの時悪い気持ちを広がらないように、私はよく家族と友達とビデオ通話して、自分の考えと不安は全て口から表現した。同時に、嬉しいことと期待することをよく考えると、自分の気持ちはだんだん落ち着きました。今まで、そんな困難と絶望をどうやって克服したのはあんまり思い出したくないけれど、生活への態度と選択は重要な役割を果たします。すべての経験は、きっと将来的に自分の貴重な資産になります。
今回の交流会に参加することで、色々な感想を浮かび上がって、本当の良い学習と交流の機会だったと思います。岸田さんへの感謝の気持ちを込めて、これからも頑張っています。
-
First of all, please let me appreciate for the powerful and hopeful speech from Kishida san. Talking about these experiences and then sharing them with the audience was really tough in my imagination, but Kishida was optimistic about what had happened to her that it stopped me from being pessimistic. From what Kishida san shared, I’m thinking about two things.
I have a cousin who had some intellectual disability in his childhood that probably prevented him from living independently in the future. Actually we all felt sad when we knew about this because it caused considerable distress to his family. But we now feel very happy with him, he has always maintained an optimistic attitude on life and hasn’t shown a great defective behavior in daily life. He can let me find out some new points in life. We asked him one time that, “Why do you smile all the time?” He answered us seriously, “It’s so happy to see you now.” His answer has largely influenced my attitude now towards others, which facing life with optimism and everyone with a smile. Most of us are not perfect in the world, but we can change our attitude on life and let our life become better.
Beijing 2022 Paralympic Winter Games are being held now, para-athletes are enjoying the topflight competitions. All of them are super powerful for me because they are doing something that I cannot do. From their efforts and their smiles, I understand even though they are physically disable, they can achieve sporting excellence so that inspire and encourage the world. From their competitions, we finally focus on their athletic achievements, not their disability. The splendor of life starts from self-action, not from the eyes of others. The first step is very tough, but once we start to do it, it will give us a great sense of accomplishment.
All in all, I hope the powerful energies what I got from Kishida san, from my cousin, from para-athletes can help, not only me but also the people around me, to be more optimistic and powerful.
Thank you very much!
-
張蘭楨
3月5日に財団の交流会として、私たちは岸田ひろ実さんと貴重な時間を過ごしました。この前に、インターネットで岸田さんの講演やインタビューのビデオをいくつか見ました。その時、私は彼女の旺盛なバイタリティにインパクトを受けました。彼女の話を聞いて、まず感じたのは、「2020年に彼女と交流する機会があれば」ということでした。交流会でもお話ししましたが、2020年は人生で最も絶望的な年でした。コロナの流行により、私の日常生活や社会一般のリズムが潰されました。 私が絶望との戦い方は、毅然とした態度で絶望に抗うことでした。しかし、岸田さんのシェアは、優しい春風のように、私の目を別の可能性に向けました。
家庭環境や学校教育のせいかもしれませんが、私たち中国人留学生の間では、家族に「喜ばしい事だけを知らせ悪い事は知らせない」という暗黙があるようです。「苦しいときは、勇気を出してSOS信号を出してください」、これほど厳粛に言われたのは初めてでした。大人になってから、毎日、親や年長者の苦労を嘆いています。従って、子どものように助けを求めることは、不可能に思えたのです。しかし、岸田さんが娘さんの話をするうちに、痛みも喜びも分かち合うことが親密関係の意味そのものなのだと、急に安心になりました。
また、岸田さんがダウン症を持っている長男の話には感動しました。確かにこの社会には、自分と違う人間に対して疑心暗鬼になり、攻撃的になる人が多いです。 しかし、不幸の根本原因は、他者に差別的な扱われたではなく、自分自身からの「異化」にあるのです。常に自分をカテゴライズし、「私みたいな人間が」「してはいけないこと」を思うと、「私」の未来への可能性や希望が失われてしまいます。「想像のギャップ」に縛られることなく、勇気を出してラベルを打ち破ってみることが大事です。
岸田さん自身の事を聞くと、中学生の時に読んだ言葉を思い出しました。作家の村上春樹さんは「高く、堅い壁と、それに当たって砕ける卵があれば、私は常に卵の側に立つ」と語りました。しかし、常に恩恵を享受してきた「多数派」である私たちは、壁の側に属すると考えがちです。日本に来てから、私は外来者、マイノリティ、弱者、つまり卵になりました。そのとき、やっと十何年前に読んだこの言葉の意味を分かりました。私たちは、上昇志向や積極性を持つよう努力するよう教えられたが、誰でも実は矛盾な存在です。「苦労している、上に行けない、ネガティブ、弱い」は、私たち一人ひとりを構成している一部です。留学生になって、初めて卵になったことは、私にとって本当に良い経験でした。「できない」、そして「普通の生活ができないこそできること」を肌で感じることにより、優しい人間になれると考えています。
-
Hu Kouzi
岸田さんの講演を聞く前に、ネットで岸田さんの履歴を簡単に調べたところ、その過去の壮絶さに言葉を失った。息子の知的障害、夫の死去、ご自身の身体障害、これだけの不幸を乗り越えた人はどんな人だろう。そして、彼女は私たちにどんな経験を教えてくれるだろう。失礼ながら、私の勝手な想像では、重々しく毅然とした女性の顔が浮かび上がった。 困ったときは強くなれと言い、「頑張ろう」と呼びかけるのではないかと思った。
実際に本人にお目にかかると、思っていたのとは全く違うことがわかった。素敵な笑顔の女性、それが岸田さんの第一印象だった。岸田さんは、表情も声もとても優しかった。背景に映る部屋は、清潔で明るかった。重苦しい雰囲気が全くなかった。この人はきっと自分の人生に愛を持っているのだろう、まだ講演の内容を聞いていなかったのに、なぜか心が明るくなった。
そして、岸田さんのお話を伺って、彼女は「頑張れ」と呼びかけるのではなく、むしろ絶望的な状況に遇う時に頑張ること以外の選択肢を教えてくれていると気付かされた。大きな不幸が降りかかるときに、それをどう克服するかを考えるのではなく、ただその日をどう過ごすかを考えていいという言葉が印象的だった。世の中には、どんなに強くても受け入れられない悲しみや、どんなに頑張ってもどうにもならないことがある。しかし、辛いことばかりに目を向けていると、視界全体が悲しいことで埋め尽くされてしまい、周りの幸せなことが見えなくなってしまう。これでは、元気が出るわけがない。岸田さんは、このような時に視点を変えることの大切さを教えてくれた。
人生には辛いことがあるが、心に愛する人がいるから、きっと幸せなこともあるのに違いがない。無理をせず、家族や友人と支え合いながら、自分にできることが現れてくるはずだ。日常への愛は、運命の無常に対する最強の武器になると、岸田さんの話を聞いて私がそう思った。
かつてイギリスの詩人ジョーン・ドンは、「人間は、だれも孤島ではない」と言った。今回の講演会を通じて、この言葉への理解が深まった。自分では支えきれないと思うとき、弱音を聞いてくれたり、痛みを分かち合ってくれたりする人がいることは、本当に大切なことだと改めて思った。気持ちが複雑で、一度には整理がつかない。しかし、この講演で得た力は、今後の人生において必ずや私の支えとなるものと信じている。
-
ZOU JUNYAN
岸田ひろみさんが語った彼女が障害者になってからの経歴のなかで私が最も感動したのが彼女は車椅子で普通にラーメン屋にもいけなく、赤ちゃん用の机でなければ座って普通に食べることもできなかったことだった。工学部の学生として、バリアフリーの社会の構築にたいする責任感を強く感じたのであった。私自身もとてもラーメンが好きでしたが、狭く椅子も高いラーメン屋に通っている時は障害者にとって普通にラーメンを好きな店で食べることはどれほど難しいことなのか考えもしませんでしたが岸田さんの言葉を聞いて初めてバリアフリーの社会の構築について考えました。自分はバリアフリーの社会が我々技術の開発に関心を持っている人の責任だと思う。近年は生体識別、自動運転のような新しい技術がどんどん進めているのに対して脚に障害がある人は相変わらず車椅子を使わざるを得ない状況にあると感じた。こんな現状にたいして、市場の選択が原因でもあるが、技術開発の偏りも無視できないほどあると言って良いだろう。けれど、こんな市場選択のなかで確かに筋電義手のような障害者向きの技術などを開発している技術者も続出していて、素晴らしい成果を見せ続けている。そこで私はバリアフリーの社会の構築は社会のあり方を変えるのではなく技術によって障害者を障害者ではないようにしてあげることこそがポイントではないかと考えた。当然、ユニバーサルマナーも大事なことだが、欧米で行き詰まりに辿ったpolitical correctnessのように誰しも受け入るはずがなく、モラルを頼って社会問題を解決することには期待できるのだろうか疑問を抱えている。それに、突然訪れる絶望に誰でも岸田さんのように前向きになれるきっかけがあるとも考えにくいだろう。従って、突然の絶望を絶望でなくなるような技術があれば、決して岸田さんのような障害を突然抱えてしまう人に負担を抱えてさせない社会が生まれるのではないだろうか強く考えるようになった。私の専門は皮肉なことに、障害者を生み出せてしまう危険なことを扱う領域だが、今後も引き続けて障害者向きの技術開発をしている研究にも目をつけたいと思う。
-
周抑揚
この度は岸田さんの話しを聞かせていただき、驚くとともに、大きく感服しました。岸田さんが経験された「三つの絶望」は、普通の人であれば、どれ一つだけを経験しても人生は大きく変わるないしは二度と立ち上がれないほどの辛いことですが、岸田さんはそれらを経験されても、なお今のように胸を張って生きている姿に感動しました。
特に、岸田さんが夫を失われて気付かれた「伝えたいことがあれば、早く伝えるべきだ。家族もいつか死別するかもしれないからだ」ということには、強く共感できます。私は小さい頃は祖母、祖父に育てられたため、祖母、祖父も両親と同じく重要な家族です。しかし、三年前に祖父は急に重病してしまい、ちょうど大学入試の直前でした。祖父は2日も持たずに亡くなり、ビデオ通話で最後を看取ることは出来ましたが、傍にいてあげることも、「ありがとう」を伝えることもできませんでした。昔は日本にいてビデオ通話はいつもできるし、何かがあってもすぐに帰国できると思って、話したいことは全部話しようと全く思いませんでした。しかし、岸田さんも経験されたように、意外はいつ訪れるかはわかりませんし、当たり前だと受け取っているものもいつか消えるかもしれません。先延ばしすればするほど、手遅れになる可能性が大きくなり、挽回しようがないことになりかねません。今回、岸田さんの話しを聞き、その悔しさを思い出しました。これからはそういうことにならないよう、家族に言いたいことをきちんと伝えようと思います。
-
董懿文
大学では心理専攻のため、障害者心理や福祉などについての授業を受ける機会がありました。しかし、授業内容は大体法律、支援側や社会の目線から物事を見ることが多く、障害者側の立場から問題を捉えることは少ないと感じます。「障害は障害者にあるのではなく、社会にあるのだ」という解釈がすごくわかりやすくて、今までの違和感が消えるようになりました。障害は、先天的も、後天的もありえることで、障害者の反対は正常者ではなく、「健常者」です。誰でも社会的障壁により、障害にあたる可能性があり、あくまでも今の段階では障害を抱えずに生活できているだけかもしれません。そのため、誰でもカバーされるように配慮していく必要があると考えられます。
岸田さんが言ったように、障害の前にまずは人として存在しています。この前に開催された「パラリンピック」に参加したアメリカのDarlene Hunter選手が言いました。体の不自由な選手たちは健常者の「inspiration porn(励みのポルノ)」ではありません。また、「inspiration porn」という言葉はオーストラリアの人権主義者であり、障害者でもあるStella Youngが作りました。その言葉の定義に当てはまる物事の一つの例としては、インターネット上によく見られる障害者の写真を使って、その横に「彼らもできるなら、あなたは何の言い訳あるの」と似たような文を加えることで、障害者を物のように扱う行為です。障害者は健常者が困難に遭遇した時に乗り越えられるための励み道具ではなく、また、どんな困難も乗り越えられるスーパーマンでもなく、障害者も非障害者も、障害の前にまずは頑張っていて、生活を送ろうとしている一人の人間だと思います。
交流会の最後に、岸田さんからすごく勉強になったことは、家族など周りの人と一緒にいられる時間を大切にして、素直に感情を伝えることが重要だと思います。人生は短く、明日はどのような出来事があるのも予測できないため、今日の一瞬一瞬をしっかり把握するしかありません。
-
葉陽光
このたび貴財団が交流会を行いありがとうございました。岸田さんの演説をうかがって心からもっと強く生きる勇気が出しました。本当にありがとうございました。
私は岸田さんが笑顔をつけながら自分の絶望を皆さんに述べることを非常に感嘆し、尊重しています。私は実に岸田さんが何度も何度も自分の絶望を話し、一回一回に傷跡をはがして大丈夫ですかと心配しています。岸田さんは絶望を経験しても、絶望から学んだことを他人にこの世界のすばらしさを伝い、皆さんに生きる勇気を渡し 教えていくことに本当に感動しました。一回だけ岸田さんと交流してもいろいろなことを勉強になることができたと思います。
岸田さんから楽観的に人生を過ごすことが大事だと体得しました。意識には強力な能動的な作用があると感じました。確かに、その感覚は実体験とはかけ離れていても、脳に痕跡を残すことはあるでしょう。私はこのような説を聞いたことがあります。健康は心の考えも一定の関係があり、健康な心であれ、素晴らしい願いであれ、体の病気を防ぐことはできます。岸田さんのように楽観的にこの世界を見て、残りの生活を幸せに生きた方が大切だと勉強になりました。
今回のオンライン交流会で、わたしのネットが悪すぎまして、ビデオが開けなく、岸田さんとの話もできなくて本当に残念でした。でも、途切れ途切れの中にも岸田さんからたくさん勉強になりました。人生の見る方も少しずつ変わり始めています。私にとって、今回の交流会は非常に意義があることだと思います。全ての人が自分の悩みがあり、重要なのはどうやってこの悩みを見るか、解決するかなのです。
最後に、もう一度わたしの感謝の気持ちを申し上げます。より良い価値観を持つ手助けをしていただきましてありがとうございました。
-
李欣宇
今回の交流会で、岸田ひろ実さんがゲストスピーカーとしてお話してくださり、自分の人生の中の4つの絶望と街で見かけるバリアフリーについて紹介していただいた。岸田さんのここ十数年の経歴を聞き、自分が今直面している様々な「困難」は全然大したことではないと覚悟し、私今後困難に立ち向かうための勇気になる話がたくさんあった。その中で、「他の人と違うことを恐れない」という話が強く印象に残り、体の不自由な人のための環境づくりに大きく啓発された。
確かに、体の不自由な人が健常者との相違点を認めたうえ、共に社会参加するための一助となり、あらゆる立場の人々に対して平等に人権の保障とする土壌が不可欠である。そして、障害者をノーマルな状態にしようとするのではなく、障害者が障害を持ったままであっても健常者と同様の生活が営めるように変えていくことを提唱するノーマライゼーションは現在の共生社会の構築にとって欠かせないと思う。障害者のあらゆる障害や制限を取り除く行動や施策は、障害者と健常者の間にあるギャップを取り払うことにつながるとともに、障害者と健常者が協働して、ともに社会参加することができるようになるのは共生社会の大きな課題で、さらにいえば、あらゆる立場の人々に対して平等にその人権を保障する環境が求められている。
しかし、振り返してみると、障害者福祉は保護施策として行われていたが、当事者である障害者主体の理念を欠いたものだという批判があった。例えば、大規模入所型施設へ送り込むことによって障害者を保護する福祉サービスは、時として当事者の要求を無視し、本人の意思を尊重しているとはいえない状況を引き起こした。こうした「施設送り」は一般社会から障害者を隔離することにつながって、障害者に対して差別や排除を意識させることもあるのではないかと思う。
従って、障害者と健常者の区別なく、社会生活を営むためには、法整備と障害者の自立を促進する支援をともに行う必要があると思う。日本では障害者総合支援法により障害者が地域社会で日常生活や社会生活を営むことを目指しており、中国でも行政条例で様々な施策がある。その中で共通しているのは、施設のバリアフリー化などの環境整備や、職能訓練と就労機会の保障といった障害者の就労支援、技術の習得などの支援であり、こうしたノーマライゼーションの思想では、障害者と健常者の間にある壁を取り払い、「他の人と違うことを恐れない」共生社会の構築や「人にやさしいまちづくり事業」の一環となる。